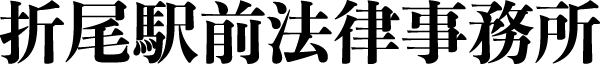お知らせ&コラム
前回は法定相続のご説明しましたので、今回は遺言相続についてご説明します。
1 遺言相続とは
遺言相続とは、「被相続人が、生前に遺産の処分を遺言という形で決めている場合の相続」をいいます。
遺言の主な類型としては、
①自筆証書遺言(民968):本人が手書きで作成する遺言(一部要件が緩和)
②公正証書遺言(民969):公証人関与のもとで作成する遺言
③秘密証書遺言(民970):遺言内容は秘密にしたいときの遺言
があり、その他にも特別な方式による遺言もあります。
2 遺言能力
遺言は、15歳に達した者が(民961)、遺言をする時においてその能力を有している必要があります(民963)。遺言をする能力を「遺言能力(=遺言内容を理解し、遺言の結果を弁職しうるに足りる意思能力)」といいますが、その判定基準は曖昧であり、あらゆる事情が総合的に考慮されるといわれています。
ちなみに、「事理を弁識する能力を欠く常況にある」とされる成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をする可能性が残されております。ただし、その場合には医師二人以上の立会い(証人とは別)のもと、その医師より遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印してもらわなければならず(民973)、成年被後見人だと印鑑証明書は抹消されており使えませんので、本人確認書類として写真入り身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要になりますし、協力する医師も見つからないことが多いため、遺言書を作成できるハードルは高いと考えられます。
せっかく遺言を残しても、その有効性が認められなければ意味がありませんので、遺言の作成を検討されている場合には早めのご検討をお勧めします。
3 遺言を有効にするためにできること
遺言が無効にならないためのリスクヘッジとしては、
①公正証書遺言にする。
②医師の診断書を添付する。
③遺言作成の過程をビデオ撮影する。
などの方法が考えられます。
平成12年3月13日付法務省民事局長通達によると、「本人の事理を弁識する能力に疑義があるときは、遺言の有効性が訴訟や遺産分割審判で争われた場合の証拠の保全のために、診断書等の提出を求めて証書を原本とともに保存し、又は本人の状況等の要領を録取した書面を証書の原本とともに保存するものとする。」とされているので、こちらも参考にするとよいでしょう。