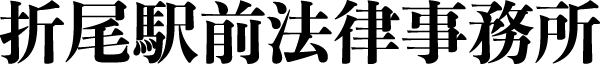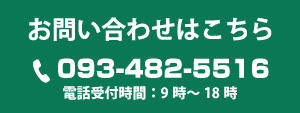お知らせ&コラム
1 特別の寄与の制度(民法1050条)とは
被相続人に対して療養監護等の貢献をした被相続人の親族(ただし、相続人は除く。)が、遺産分割の当事者となることなく、遺産分割の手続外で、相続人に対して寄与の程度に応じた金銭請求をすることを認める制度です。
民法の改正により新設され、2019年7月1日以降に開始した相続について適用されています。
2 制度創設の経緯
民法には、従来から「寄与分」(民法904条の2)という制度がありましたが、これは被相続人に対して療養監護等の貢献をした「相続人」が相続財産から分配を受けることを認める制度で、相続人にのみ認められるものでした(この制度は現在もあります。)。
しかし、相続人の配偶者が療養監護に努め、被相続人の財産の維持または増加に寄与しても何らの請求もできないなどの実情が生じ、その不公平を是正するために「特別の寄与」の制度が新設されたのです。
3 請求できる人とは
特別の寄与を請求できるのは、「相続人を除く被相続人の親族」です(正確には、親族から相続人及び相続放棄者、相続欠格該当者、推定相続人の排除者が除外されています。)。
これは、一定の人的関係にある者が被相続人の療養監護等をした場合には、被相続人との間で有償契約を締結するような対応が困難であることから限定されたもので、明確化のため、判断基準時点は相続開始時の親族と解されます。ちなみに、「親族」とは、六親等内の血族と配偶者、三親等内の姻族を指します(民法725条)。
4 特別の寄与が認められるためには
特別の寄与と認められるためには、「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加」したことが必要です。
具体的には、訪問看護等のサービスを受けなくても済む程度の療養看護をした場合や、被相続人の事業に対して無償で労務の提供をした結果被相続人の財産が維持や増加した場合などが挙げられます。無償性の判断については、被相続人が生活費を負担してあげてからといって直ちに否定されるのではなく、個別具体的に判断されることになるでしょう。
5 寄与の程度に応じた金銭とは
特別の寄与が認められる場合、その具体的な金額は1次的には当事者間の協議で決められます。当事者間で協議が整わない場合や、相続人の1人が行方不明で協議をすることができないときは、家庭裁判所に対し協議に代わる処分の請求することができます。
この場合、特別寄与料の額は、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」すると定められています(1050条2項3項)。一切の事情には、相続債務の額や遺言内容、遺留分、特別寄与者の生前の利益等が含まれると言われています。この点は、寄与分と類似することから、寄与分を参考することになると思われます。
なお、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(民法1050条4項)。
(算定例)
療養監護型:第三者が同様の療養監護を行った場合における日当額に日数を乗じた上で、一定の裁量割合(人間関係から)を乗じて算定など
6 請求の相手方
請求できる相手方は相続人であり、相続人が複数であってもそのうち1人を相手方とすることもできます。ただし、1人に対して請求できる金額は、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分又は指定相続分(民900~902条)を乗じた額に留まります。
7 期間制限
特別寄与者が家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる期間は「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヵ月」以内及び「相続開始の時から一年」以内とされ、いずれも除斥期間と解されています。