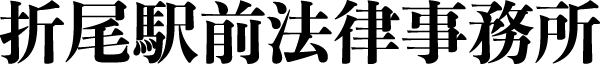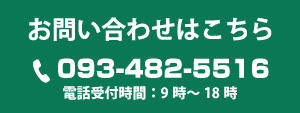お知らせ&コラム
1 刑事責任能力とは
責任能力は、講学上の意義としては、一般に、「行為者に有責に行為をする能力、すなわち事理の是非・善悪を弁職し、かつ、それに従って自己の行動を制御できる能力」などと定義されます。
もっとも、責任能力とは法令上の用語ではなく、これに該当すると思われる刑法39条では「心神喪失」及び「心神耗弱」という言葉が使われています。
2 心神喪失とは
心神喪失とは、「精神の障害(①)により事物の理非善悪を弁職する能力がなく(②)、又はこの弁職に従って行動する能力のない(③)状態」を指し、この場合は罰しない、すなわち無罪となると規定されています。
①は生物学的要素ですが、②(弁別能力)と③(制御能力)は心理学的要素にあたります。(=動機の了解可能性、行動の合理性、犯行態様など)。
②を簡単に言えば、「やってよいこととやってはいけないことを判断する力がないこと」であり、③を簡単に言えば、「やってはいけない行為を抑える力がないこと」を指します。
3 心神耗弱とは
「精神の障害が、②③を欠如する程度に達しないものの、著しく減退している状態」
を指し、この場合は刑を減刑することになります。
4 判断方法
責任能力の判断主体は、裁判所です。(法律問題。不拘束説)
そして、判断手法としては、総合的判断方法が採られており、具体的には
「鑑定書全体の記載内容とその余の精神鑑定の結果、並びに記録により認められる被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して」判断されることになりますが(最判S59.7.3刑集38巻8号2783頁)、
「責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について、専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、裁判所は、その意見を十分に尊重して認定」されることになります(最判H20.4.25 最高裁刑事判例集62巻5号1559頁)。
また、総合考慮を行う際には、被告人の病的体験と犯行との関係、被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度が重視される傾向にあるようです(最判H21.12.8刑集63巻11号2829頁)。
5 鑑定とは
鑑定には、①留置を伴わない起訴前鑑定(簡易鑑定)、②留置を伴う起訴前鑑定、③公判鑑定、④弁護人依頼の鑑定、があり、主な内容は次のとおりです。
①簡易鑑定:起訴前に捜査機関が終局処分を決めるための参考にする目的で実施する簡易な鑑定で、鑑定留置を伴わないため通常の勾留期間中に行われるもの。
②(検察官の嘱託による)起訴前鑑定:起訴前に捜査機関が実施する鑑定で、鑑定留置による病院施設での留置を含む本格的な鑑定。起訴前本鑑定。
③公判鑑定:裁判において裁判所が職権で行うもの(刑事訴訟法165条)で、審理期間中に一定期間を空けて鑑定を行うもの。一般に弁護人からの鑑定請求に対して行うことが多い。
④弁護人による鑑定:被疑者ないし被告人が自ら費用を捻出して医師に依頼して鑑定をしてもらうもの。
6 責任能力を争う場合
資力があれば、弁護人による鑑定を行い、有利な鑑定であれば証拠で出すことを検討することが可能です。
そうでなければ、弁護人から、検察官に対し簡易鑑定などの申し入れをする、公判で裁判所に対し鑑定請求を行うなどの対応をしていく必要があります。
裁判所において、鑑定は必要ないとして鑑定請求を却下する決定をされた場合には、その採否決定に対して異議申立をすることも可能です(刑訴規則205条の2)。その場合には、法令違反であることの指摘しなければならない(規則205条1項)ため、「裁判所の裁量を逸脱した不合理なものであり、違法である。」などと指摘することになるでしょう。