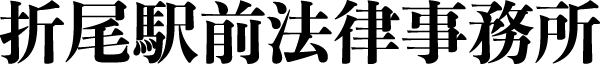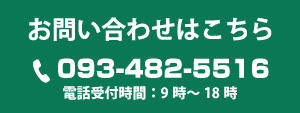お知らせ&コラム
交通事故により、胸腰椎等が圧迫骨折するなどしたことにより、脊柱変形の後遺障害が残存することがあります。
1 脊柱の構造及び役割について
①脊柱の構造について
脊柱とは、頭蓋骨から尾骨まで延長している脊椎の連続で、「脊髄を支え、可動性のある骨の枠を形成しているもの」と定義され、その詳細は7個の頚椎、12個の胸椎、5個の腰椎、5個の椎骨が癒合して塊椎となった仙椎及び、数個の尾骨に区分されます。
そして、個々の椎骨は腹側の椎体と背側の椎弓から成り、その間に椎孔を囲み、それが脊柱管として、その内部に脊髄が入っています。
全体を横から見れば、頚椎は凹弯、胸椎は凸弯、腰椎は凹弯し、椎骨(椎体)と椎骨(椎体)の間には椎間板が存在し、クッションとして衝撃を和らげる役割を果たしています。
②脊柱の機能
おおまかにいうと、「支持機能」と「運動機能」があります。
「支持機能」は、椎骨及びその他の総合的作用によって、内在支持機構を有し、その周辺の筋等により外在支持機構によって補強されています。
「運動機能」は、脊柱各部の協同運動によって前後左右屈や上下運動、回線運動を可能とするものです。
さらに、脊柱には、「脊髄保護」という重要な役割も果たしています。
2 「脊柱の変形」の後遺障害について
脊柱変形は骨折によって生じることが多く(脱臼等もありえます。)、治療の方法としては、手術による固定術(手術的療法)もあるようですが、骨折の癒合を待つ保存的療法が選択されることが多いと思われます。
自賠責保険における脊柱の変形障害としては、
①脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)
②脊柱に中程度の変形を残すもの(8級に準ずる)
③脊柱に変形を残すもの(11級7号)
の3段階で認定されます。
3 労働能力喪失率の争いについて
後遺障害が残存する場合、それに伴って将来的な収入も減少することが見込まれることから、事故に遭わなかったら得られたであろう収入の減少分を逸失利益として請求することができるのが一般的です。
ところが、脊柱の変形については、従前より加害者から、
脊柱変形自体による逸失利益は認められない、
仮に逸失利益が存在してもそれは脊柱変形に伴う痛みによる逸失利益が認められるのみである(労働能力喪失率14%程度、労働能力喪失期間10年程度など。)
などとして、労働能力の喪失が認められるか否かが争われることがあります。
労働能力を否定する考え方としては、変形があってもそれに伴って脊柱の安定性や保持性自体に支障はないというもので、特に「11級の脊柱変形では労働能力の喪失はほとんどないに等しい」との見解や「他の系列の障害度との公平性を図るため、12級に引き下げる」べきとの見解がみられます。
もっとも、脊柱の変形障害は、
「脊柱の支持機能・保持機能に影響を与え(、又は与えるおそれがあ)ることに対するものと理解される」との視点のもとに検討され、11級との位置づけは他の11級等級と比較しても不合理とは考え難い、として定められたものであるため、安易にこの等級より低い喪失率を認める理由はありません。
脊柱の損傷は、支持性と運動性の二つの機能を減少させるものであり、進行性の脊柱変形が惹起されるおそれがあるほか、骨折局所等に疼痛と疲れやすさが残ることもあります。
脊柱変形が被害者の労働能力に対しどのような影響を及ぼすかについては、被害者の年齢、性別、職業、骨折の部位・程度、骨折自体の安定性の有無、神経症状の有無、脊髄障害の有無、治療法の適否、固定術の方法などの諸事情を総合的に検討して判断することになるでしょうが、高度の脊柱変形は、脊椎の骨折という器質的異常により脊椎の支持性と運動性を減少させ、局所等に疼痛を生じさせ得るものであるという点を重視すると、原則として喪失率表の定める喪失率が相当でしょう(赤い本 2004年(平成16年)片岡裁判官講演録)。