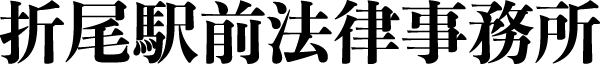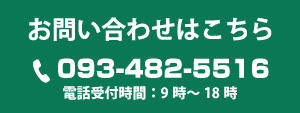お知らせ&コラム
1 更新拒絶等にかかる正当事由について
建物を生活や営業の基盤として利用している賃借人にとって、賃貸人から更新拒絶の通知や解約の申入れだけで、契約が終了して建物の退去を強いられてしまうと多大な不利益を被るおそれがあります。
そこで、借地借家法28条は、期間の定めのある借家契約の更新を拒絶する、あるいは期間の定めがない借家契約の解約の申入れをするためには、「正当事由」を必要としており、その考慮要素として、
①賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、
②建物の賃貸借に関する従前の経過、
③建物の利用状況、
④建物の現況、
⑤賃貸人が財産上の給付(立退料の支払)をする旨の申出をした場合におけるその申出
が規定されています。
これらの考慮要素の中でも①が基本的な考慮要素であり、②~⑤は補完的なものと解されています。そのため、立退料(⑤)の申出のみで正当事由が認められるものではなく、他の諸般の事情と総合考慮され相互に補完しあう形で判断されることになります。
深くは立入りませんが、①賃貸人側の建物使用の必要性として主張される事情の多くは、建物の老朽化や耐震性不足を理由に建て替える(再開発も含む)というものであり、建替えの必要性が高い場合にはその事情を重視し(④の要素も含まれる。)、立退料の引換えに建物明渡請求を認容される傾向にあるようです。
2 立退料の位置づけ
前記のとおり、立退料の支払は正当事由判断において補完的考慮要素であり、その金額が明渡しによって賃借人が被る損害の全てを補償するに足りるものである必要はなく、その具体的金額を正確に説明できることも求められておりません。
立退料の性質については諸説ありますが、概ね
「移転費用(引越料や礼金・仲介手数料その他移転実費)の補償」と
「賃借人側が事実上失う利益(転居後の賃料と現賃料の一定期間の差額分や営業損害など)の補償」
が補償対象となることが通常です。
これに加えて、明渡しによって消滅する「借家権自体の補償」も認められることがありますが、その場合には借家権自体に認められる財産的価値(借家権価格)を算定することになります。算定については、不動産鑑定評価基準に基づくことが一般的であり、場合によっては不動産鑑定士の協力も必要となります。
現在、高度経済成長期に建設された多くの建物の老朽化が進んでいるため、建て替え等を理由とする建物明渡に関する紛争も増加していくことが予想されます。
立退料は、建物明渡に付随して問題となってくるため、しっかりとした専門的知識をもって臨むことが必要です。
立退料の請求する側もされる側も、どうすべきか不明な場合は専門家に相談することをお勧めします。