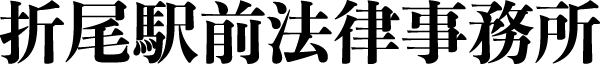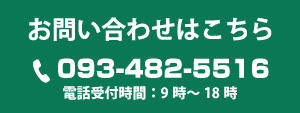お知らせ&コラム
1 個人再生における「住宅資金貸付債権に関する特則」とは
法的な債務整理においては、原則として、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないため、一部の債権者に対してのみ支払いをすることはできません。そのため、住宅ローンを抱えている場合には、住宅ローンの債権者(金融機関等)に競売を申し立てられ、家を失ってしまうリスクがあります。
ところが、個人再生手続においては、自宅を残して債務整理を図ることができる方法が残されており、これが「住宅資金貸付債権に関する特則」と呼ばれます。これを利用すると、住宅ローンとそれ以外の消費者金融などの借金を抱えているとき、消費者金融などの借金だけを減額することができるのです。
(少し難しい説明となりますが、住宅資金特別条項(内容は下記「3」参照。)を定めた再生計画(返済計画)の効力を、住宅に設定されている住宅ローンの抵当権にも及ぼすこととし(民再203条1項)、再生債務者が再生計画に基づく住宅ローンを弁済している限り、その抵当権の実行を回避できるようにする特則がこれに当たります。)
2 どのような場合に利用できるか(要件充足性)
個人再生手続であれば、全ての場合に特則が利用できるわけではなく、次の要件を満たす必要があります。
① 自己所有(共有)の居住用の住宅であること(民再196条1号)
「再生債務者が所有し自己の居住の用に供する建物であること」
仮に、再生債務者が現に自宅に居住していない場合には(単身赴任し、家族の暮らす本拠と赴任先の住居がある場合等)、今後自宅に戻る予定の有無やその時期等を考慮して判断されます。
「建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が、専ら居住用に供されること」
例えば、「二世帯住宅」や「店舗兼居宅」等の場合、債務者自身の居住のために使用する部分がどの程度であるか、登記の種類が「居宅・倉庫ないし事務所」等になっていないかなどを検討することになります(平面図や間取り図、陳述書等の提出が必要となることもあります。)。
「自己の居住の用に供する建物が二以上ある場合には、主として居住の用に供する一の建物であること」
② 住宅資金貸付債権であること(民再196条3号)
「住宅の建設若しくは購入に必要な資金、又は、住宅の改良に必要な資金の貸付けによって生じた分割払の定めのある再生債権であること」
例えば、「借換えが行なわれた場合」には、その借換えのための貸付けに係る債権も、当初の借入れが住宅資金貸付債権の要件を満たし、かつ借り換え後のローンに住宅資金貸付債権以外の債権が混入していない必要があります。
また、購入資金とは別に、仲介手数料、登記手続き費用、各種税金、保険料等の諸費用もローンを組む、いわゆる「諸費用ローン」の場合には、使途や額などを総合的にみて許されないか、慎重に検討しなければなりません。
「当該債権又は当該債権に係る債務の保証会社の再生債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているもの」
住宅に根抵当権が設定されている場合であっても、その被担保債権が住宅資金貸付債権のみであると認められるときは、要件を満たすと思われます。
③ 住宅又は共同担保の他の不動産に後順位別除権が設定されていないこと(民再198条1項)
住宅を担保として、車のローンなど住宅ローン以外の借入れをしている場合には、住宅資金特別条項を利用することができません。
特に、マンション管理費等は特別の先取特権に該当し、滞納していれば別除権となるため、要件を満たさなくなってしまいます。場合によっては、滞納の解消を検討すべきでしょう。
④ 保証会社が代位弁済した場合で代位弁済日から再生手続申立まで6カ月を経過していないこと(民再198条2項)
保証会社が代位弁済しても6ヵ月以内であれば、住宅ローンは復活できます(いわゆる「巻き戻し」民再204条)。
再生手続開始を申し立てる際には、さまざまな書類が必要になりますので、この場合には早急に準備しなければなりません。
3 「住宅資金特別条項」の内容
住宅ローンの返済内容としては、次のとおりに分けられます。
①約定弁済型・そのまま型(民再199条1項)
住宅資金貸付債権について支払いを継続することで(ただし、申立後は許可を得る必要があります。)、期限の利益を喪失していない場合に、当初の住宅資金貸付契約の弁済期・弁済額の約定のまま支払うものです。
②期限の利益回復型(民再199条1項)
住宅資金特別条項の原則型で、遅滞に陥っている部分と契約上の債務を計画期間内に弁済することで、再生手続開始前に発生している期限の利益喪失の効果を失わせるものです。遅滞部分の弁済方法は一括でも分割でも構いません。
③リスケジュール型・弁済期間延長型(民再199条2項)
②による計画認可の見込みがない場合に、利息と損害金を含めて全額弁済することを前提に、支払期限を最大10年間、債務者が70歳を超えない範囲内で延長し、各回の支払額を減らすものです。
④元本猶予期間併用型(民再199条3項)
③に加えて、再生計画期間内は元本の一部の弁済の猶予を受け、他の債務(一般再生債権)の弁済と調和した弁済計画をするものです。多くは、元本猶予期間を再生計画で定める弁済期間(原則3年)と同じ長さに設定されていると思われます。
⑤合意型(民再199条4項)
住宅ローン債権者の同意(書面によることが必要。民再規100条)がある場合には、上記条件とは異なる内容をもつ条項を定めることも可能です。
4 さいごに
個人再生計画は裁判所の認可決定を得なければなりませんが、「住宅資金特別条項を定めない場合」と「定めた場合」では、定めた場合の不認可要件の方が次のとおり厳しくなります。
「住宅資金特別条項を定めない場合」:「再生計画が遂行される見込みがないとき」に不認可となる(民再174条2項2号)
⇔
「住宅資金特別条項を定めた場合」:「再生計画が遂行可能であると認めることができないとき」に不認可となる(民再202条2項2号)
以上が主な概要ですが、ここまで記載したものの他にも、住宅資金特別条項を定めた上での個人再生には、多くの注意点があります。実際には、申立前から住宅ローン債権者や裁判所と協議しながら進めていく必要がありますので、しっかりとした専門知識をもった代理人と協議しながら進めていくことが望ましいと言えます。