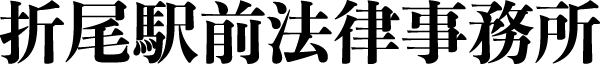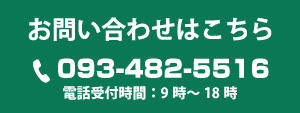お知らせ&コラム
1 不動産競売となる場合とは
住宅ローンなどで不動産に抵当権を設定している場合や、借金を滞納して裁判となり判決(債務名義)を取得されている場合などで、債務を支払うことなく放置しておくと、不動産の競売に踏み切られてしまうことがあります。
もっとも、不動産競売が申し立てられた後でも、債権者と取下げ交渉をすることで、競売の申立てを取り下げてもらえる場合があります。
2 債務者が不動産競売の申立てを知るのはいつか。
不動産競売の申立ては、対象不動産所在地を管轄する地方裁判所に対して行います(競売の取下げも同様)。
債務者が自身の不動産が競売手続きに入ったと知るのは、裁判所からの「競売開始決定通知」が届いた時点(特別送達)がほとんどだと思います。
「競売開始決定通知」が届いたということは、債務者が所有する不動産を競売により売却する手続きを始めますという裁判所からのお知らせが届いたということです。
3 とりうる対策
すでにネットで情報は溢れているかもしれませんが、競売の開始決定を受けた債務者がとりうる対策は、主に
①債務の返済(→取下げだけでなく、執行異議もできます。)
②任意整理
③任意売却
のいずれかだと思われます。
もっとも、お金があればきちんと返済しているはずなので、どこかからお金が捻出できない限り、①債務の返済の現実的可能性は低いと思います。
これに対し、③任意売却は競売よりも高い価格で購入してもらえる買主を見つけて債権者と交渉し、債権者が納得できる条件や額での任意売却を提示することで、競売の取り下げをしてもらうというもので、もっとも現実的な手法です。
ただし、高い金額での売却は債務者にも大いにメリットがありますが、結局は不動産を手放さなければならないことに変わりありません。
そこで、考えられる手法は②任意整理で、金額を下げてもらって一括返済や分割返済の交渉をして合意が得られたら取り下げをしてもらうというものです。
ただし、これもなかなかハードルが高く、最近では、貸金業者も厳しく、元本の一括返済や直近の遅延損害金を含めた分割しか応じない傾向があるように思えます。
4 取下げ可能期間
いずれの対策をとるにせよ、取下げが可能な期間は限られますので、期間に注意しなければなりません。
流れとしては、下記のとおりであり、一般的に「競売開始決定通知」から「売却実施後に買受人が代金を納付するまで」の間が、不動産競売の取下げ可能期間ということになります。(この間の目安はおよそ5~6ヶ月くらいと思われます。)
「競売開始通知」
↓ 1~3月以内くらい
「現況調査」(執行官と不動産鑑定士が現地に来て調査をする。)※強制力があります。
↓ 2~4月以内くらい
「期間入札通知」(入札期間や開札日など具体的日程や売却基準額の決定)
↓ 2ヶ月以内くらい(この間に「期間入札の公告」があります。)
「期間入札開始」
↓ 1週間くらい
「開札」(締切で落札者が決定する日)
↓ 数日内
「売却許可決定」
競売申立の取下げは、理論上、「開札」前日までは可能です。ただし、債権者も通常金融機関や債権回収業者といった会社であり、社内の稟議等があることを考慮すれば、ある程度余裕をもった時間がなければなりません。目安としては、「期間入札通知」前までくらいと考えた方がよいでしょう。
さらに、競売には、差押登記の嘱託や現況調査、不動産の評価などの手続の際に費用がかかるため、あらかじめ申立債権者に予納金を納めさせ、裁判所が不動産競売の各種手続でそれを費用に充てる形を取っています。
このような費用が積み重なっていくため、交渉が遅れれば遅れるほど申立債権者は取下げに応じなくなっていくことが考えられます。
なお、開札により落札者が決まった後でも、落札者の同意を得ることができれば、代金が納付されるまでは競売取り下げが可能です。(もっとも、落札者も競売に対してコストが掛かっているため、落札者が取り下げに同意する可能性はほぼ無いと考えた方がよいでしょう。)
5 申立取下の手続き
当たり前ですが、取下げは申立債権者のみ行うことができます(ただし、債務全額弁済であれば執行異議も可能。)。
そのため、流れとしては、申立債権者と何らかの合意をし、管轄の地方裁判所に対して申立債権者から取下書を提出してもらうことになります。
なお、取下書の印鑑は原則、競売申立書に押印した印鑑と同一でなければなりませんので、注意が必要です(債務者からも注意喚起をしておくといいでしょう)。
競売取下に伴い差押登記の抹消嘱託をするため、その際に登録免許税を納めなければなりません。(不動産1個につき、1000円の印紙が必要。)
6 競売取消しとなる場合
これまで取下げについて述べてきましたが、これとは別に競売が取下げになる場合もあります。
具体的に取り消しになる場合とは、
①競売して換価しても、手続費用や優先債権者(抵当権者や税債権を有する自治体等)の債権額の合計額より下回り、申立債権者に配当が行く見込みがない場合(民事執行法63条)※ただし優先債権者の同意を得た場合は例外
②競売物件が火災などにより滅失した場合(民事執行法53条)
③3度売却を試みても売却の見込みがなく、申立債権者が売却実施の申出機会を与えても売却の見込みがない場合(民事執行法68条の3)
といった場合です。
ただし、競売による返済すらできないということですので、当然債務は残ります。