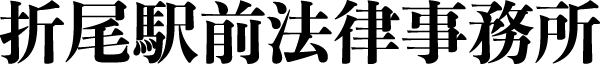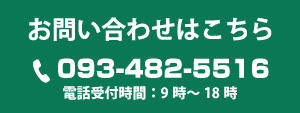お知らせ&コラム
1 はじめに
自動車による交通事故に遭って怪我をした場合、相手方の強制保険である自賠責保険から直接支払いを受けることができる場合があります(自賠法16条 被害者請求)。
ただし、被害者が自賠責保険以外から支払いを受けることができた場合、多くがその支払いをした金額の限度で支払者に被害者請求権が移転することと規定されています(直接請求権の代位取得)。
そのため、填補されていない部分の損害賠償を求める被害者の被害者請求と、被害者請求を代位取得した支払者の請求が競合してしまうことがあります。
本コラムでは、競合する請求を受けた自賠責がどのように支払いをすべきかの問題(自賠責保険における被害者の直接請求権と代位取得された直接請求権との関係))につき、現時点までの裁判例を整理して説明いたします(令和7年9月18日時点)。
2 最三小判平成20年2月19日(民集62巻2号534頁)
本件は、自動車事故の被害に遭い老人福祉法に基づき大阪市の負担にて医療を受けた被害者が、医療費以外の填補されていない損害につき自賠責保険に被害者請求をしたところ、老人福祉法に基づき医療費を負担した大阪市もその負担の限度で自賠責保険に直接請求をしていたという事案です。被害者の行使する直接請求権の額と大阪市の行使する直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えていたことから、相互の関係が問題となりました。
この点につき、最高裁は、
①自賠法16条1項は、被害者が自賠責保険金額の限度では確実に損害の填補を受けられることにして、その保護を図るものであるから(同法1条参照)、被害者に自賠責保険金額を超える未填補の損害が存在するにもかかわらず、自賠責保険金額全額の支払を受けられないというのは、同法16条1項の趣旨に沿わないこと、
②老人保健法に基づく医療の給付は社会保障の性格を有する公的給付であり、市町村長において被害者の第三者に対する損害賠償請求権を取得するのは、医療に関する費用等を当該請求権によって賄うことを目的とするものではなく、市町村長が直接請求権を行使することによって、被害者の未填補の損害に係る直接請求権の行使が妨げられるのは同法41条1項の趣旨にも沿わないことから、
被害者が未填補の損害について直接請求権を行使する場合は、医療給付を行った市町村長が取得した直接請求権を行使し、両請求権の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、被害者は市町村長に優先して自賠責保険から保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができる
と判断しました。この判断は、被害者優先説を採用したものと理解されています。当時、自賠責保険は各請求権の額で案分する処理をしていたようですが、本判決以降は被害者優先説に従った取扱いがされているようです(老人保健法の事案に限らず健康保険等の事案においても同様)。
3 最一小判平成30年9月27日(民集72巻4号432頁)
本件が、業務災害として自動車事故に遭った被害者が、労災保険給付(療養補償給付及び休業補償給付、障害補償給付)を受けたところ、未填補の損害を求めた被害者の行使する直接請求権と労災の代位取得した直接請求権が競合したという事案です。上記の判例はありましたが、労災保険の事案では案分説に従った保険実務の運用が維持されていたため、本件では労災保険との関係での取扱いが問題となりました(労災保険給付は損害填補を目的とする、あるいは損害填補に当たる給付が含まれる点で健康保険等の給付とは異なるとの解釈に基づく運用だったと思われます。)。
最高裁は、自賠法16条1項が被害者の直接請求権を認めた趣旨(確実な損害填補)及び労災保険法12条の4第1項が求償権の代位取得を認めた趣旨(重複取得の排除及び賠償責任者の賠償義務免脱の回避)に鑑み、
被害者が未填補損害について直接請求権を行使する場合は、労災給付を行い国に移転した直接請求権が行使され、被害者の直接請求権の額と国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で自賠法16条1項に基づき損害賠償額の支払を受けることができる
と判断しました。これにより、労災保険についても被害者優先説が採用されたと評価できます。
4 最一小判令和4年7月14日(民集76巻5号1205頁)
この事案は、「3」と同様に、被害者の直接請求権と労災の代位取得した直接請求権が競合したものですが、保険会社が国の請求に対し全額を支払った後に被害者から請求を受けたため、その場合の取り扱いや各請求権に対する保険会社の支払の有効性が問題となりました。
最高裁は、上記「3」の平成30年最判の判断(被害者優先説)を踏襲した上で、
このことは、被害者又は国が上記各直接請求権に基づき損害賠償額の支払を受けるにつき、被害者と国との間に相対的な優先劣後関係があることを意味するにとどまり、自賠責保険の保険会社が国の上記直接請求権の行使を受けて国に対してした損害賠償額の支払について、弁済としての効力を否定する根拠となるものではないとし、被害者の有する直接請求権の額と、労災給付を行い国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても、自賠責保険の保険会社が国からの請求を受けて国に対して自賠責保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たる
と判断しました。
この場合、国が、上記支払を受けた額のうち被害者が国に優先して支払を受けるべきであった未填補損害の額に相当する部分については、被害者に対し、不当利得として返還すべき義務を負うことになると思われます(同旨を最高裁も示唆しています。)。