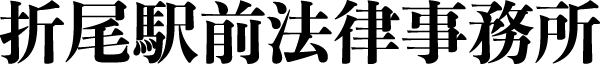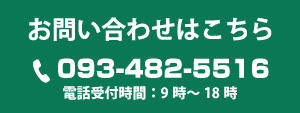お知らせ&コラム
1 遺言の有効性が問題になる場合
遺言が残された場合でも、その法律行為たる遺言が当初から又は現在その効力を有しないとして有効性が争われる場合があります。そのような争いが訴訟となった場合、その事件は遺言無効確認請求事件といいます。
2 遺言の無効原因
遺言の主な無効等の原因としては、①方式違背(民法960条)、②遺言書の偽造(自筆証書遺言の自書性)、③公序良俗違反(民法90条)などの一般的有効要件の欠如、④遺言無能力(民法961条ないし963条)、⑤錯誤や詐欺取消(民法95条・96条)などが挙げられます。
このうち、特に主張されるのが、遺言当時には遺言能力がなかったこと(④)、及び遺言が偽造されたものであること(②)です。
3 遺言無能力(④)が争点の場合
遺言能力とは、有効に遺言をする精神能力のことをいいます。
法律上、民法961条で15歳に達することを求めていますが、民法962条が行為能力に関する総則規定が排除していることから、年齢要件のほかは意思能力を有することを求めているのみと解されます(民法963条)。
このような遺言能力の存否の判断に当たっては、主に遺言時における遺言者の精神上の障害の存否及び内容・程度、遺言内容それ自体の難易性、遺言の動機・理由や遺言者と相続人・受遺者との人的関係・交流状況、遺言に至る経緯等が総合考慮されることになると解されています。
・遺言時における遺言者の精神上の障害の存否及び内容、程度
遺言能力の判断において最も基礎的かつ重要な事情です。
具体的には、精神医学的観点から精神疾患があったかどうか(典型的には、認知症、統合失調症、意識障害など)につき、基本的には遺言時ないし遺言前後の診断書や医師の供述、その後の事情(成年後見開始など)をもとに検討され、これを補完する形で遺言時ないし遺言前後の症状や言動といった行動観察的観点からの検討もされます。
・遺言内容それ自体の難易性
遺言内容の難易は、遺言能力が遺言内容で相対的に定まる以上、遺言能力の有無の判断に大いに関係します。例えば、「1人にすべての財産を与える」とか「居住不動産を住んでいる者に与える」といった内容は「単純」「理解しやすい」と評価されやすく、信託銀行の作成するような遺言は「複雑」と評価されることが多いといえます。
簡単な内容であれば求められる遺言能力は高いものではなく、複雑な内容であれば求められる遺言能力は高まることになります。
・その他の事情
意思能力がある場合に合理的な判断をし、そうでない場合に不合理な判断をすることが多いと考えられるため、遺言内容の合理性も遺言能力の判断において重要な要素となります。この点は一概にはいえませんが、よく世話をしてくれた人に多くを残すことは合理的と判断されやすく、逆に一切交流がなかった人に多くを残すことは不合理と判断されやすい傾向にあるでしょう。
公正証書の場合、例外的な方式もありますが、基本的には公証人への嘱託・本人確認はもちろん、証人2名以上の立会い、口授・筆記・読み聞かせ(遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が筆記、読み聞かせ又は閲覧させること)、遺言者及び証人の署名押印という法定の手順を踏んでいるため、有効とされる可能性が極めて高いです。
4 遺言書の偽造(②)が争点となる場合
自筆証書遺言の自書性が争われる場合ですが、この場合には
筆跡の同一性、遺言者の自書能力の存否及び程度、遺言書それ自体の体裁等(インクや朱肉の色合いや濃淡、言葉遣いや時期と文章内容との整合性など)、遺言書の保管状況や発見状況などが重要な判断要素となります。
以上に加え、遺言能力の判断要素とも重なりますが、遺言内容の複雑性や合理性、遺言に至る経緯、人的関係も重要な事実となると考えられます。