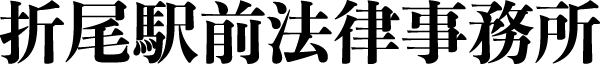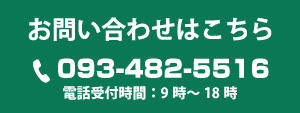お知らせ&コラム
1 建物収去土地明渡請求権保全のための建物の処分禁止仮処分とは
借地人がその土地上に建物を所有している場合、借地権が解除などにより消滅すると、その土地上の建物を収去して当該土地を所有者に明け渡さなければなりません。
また、土地の不法占有者がその土地上に建物を所有している場合も、不法占有者はその建物を収去して土地を明け渡さなければなりません。
このとき、義務者がその義務を任意に履行しないときには、土地の所有者は建物名義人に対し、建物収去土地明渡しの訴えを提起することになります。
しかしながら、その建物について第三者(相続人は除外)への所有権移転登記がされてしまうと、その訴えの相手方を変更しなければならず、また、勝訴の確定判決を得ても、判決による執行ができなくなるおそれがあります。
そのため、そのような責任転嫁が行われる可能性がある場合には、事前に、建物収去土地明渡請求権を保全するため、建物の所有者を債務者として仮処分命令の申立てをし、債務者(建物の所有者)に対して「当該建物の処分禁止の仮処分」を得る必要があります。
この建物の処分禁止の仮処分命令が出された場合、保全執行裁判所の裁判所書記官が、直ちにその仮処分の執行として、処分禁止の登記を行います(民事保全法55条1項・2項、47条3項)。
2 処分禁止の仮処分及び登記の効力
この処分禁止の仮処分は、債務者(建物の所有者)に対してその建物の処分を禁止するものであり、これに反して処分がされた場合でも、仮処分債権者に対する関係においては、その処分は無効となります。
すなわち、この登記がされた後に建物が債務者の処分により第三者に譲渡されても、仮処分債権者が建物収去土地明渡の勝訴判決等の債務名義を得た場合には、その建物の譲受人に対してその債務名義に基づき建物の収去及び土地明渡しの強制執行をすることができる効力があります(民事保全法64条)
3 その他関連する保全処分について
建物の名義ではなく、事実上の占有の移転を制限したいのであれば占有移転禁止の仮処分を申し立てる必要があります。例えば、建物の所有者が第三者に建物を貸し出すなどして占有のみを第三者に移転した場合、処分禁止の仮処分には、建物の占有の移転を禁止する効力はありませんので、第三者に対して建物退去土地明渡しの訴えを提起する必要性が生ずる可能性があります。
また上記の処分禁止の登記は、登記後にされた第三者の所有権移転登記を抹消することまでは認められておらず、抹消するためには登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分を必要があるとされています。
4 まとめ
土地の明渡しを求める訴訟をしなければならない場合、相手方の言動や態度、その他具体的事情にもよりますが、上記のような複雑な仮処分の検討が必要となります。
保全手続については、より専門知識が必要となりますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。